こんにちは!せこかんくんです。
今回は、一級建築士製図試験、要点記述の構造についてまとめました。
何度も読んだり書いたりして知識として定着させましょう。
地盤条件や経済性を踏まえた、支持層の考え方、採用した基礎構造とその基礎底面のレベルについて考慮したこと
建築物をN値30以上の砂礫層へ支持させるために適切な基礎形式として、根入深さ◯mのべた基礎を採用した。
既存建築物撤去範囲の埋戻し部分は、地盤の強度が不明なため、基礎下から深さ◯mまでを表層改良を行い、不同沈下に対処できるものとした。
建築物の構造計画について、建築物の特性に応じて採用した構造種別・耐震計算ルートと耐震性を確保するために考慮したこと
ルート3
純ラーメンとした靱性の高い建築物とするために、柱・梁のせん断補強筋を密にした。
柱の曲げ降伏を避け、梁降伏先行となるように、梁の耐力に比べて柱の耐力が大きくなる断面寸法、配筋とした。
大空間の天井落下防止対策について考慮したこと
室用途、天井高さ及び天井の水平投影面積等から特定天井に該当するため、平成25年基準に準ずる計画とした。
地震時の変位を抑制するため、吊り材の長さは1.5m以下とした。
天井の破損を防ぐために、壁と天井の取り合い部分には6cm以上のクリアランスを確保した。
建物全体の構造種別・架構形式、スパン割り・主要な部材の断面寸法について考慮したこと
耐火性、遮音性、耐久性に優れた鉄筋コンクリート造を採用した。
平面計画の自由度が高いラーメン架構とした。
経済的で安定した部材断面寸法とするため、X方向、Y方向を均等スパンで計画した。
| 大梁:500×800 | 柱:700×700 |
| 小梁:300×600 | 壁:150 |
| 床:200 |
大梁は、スパンの1/10以上の梁せいを確保
無柱の大空間を踏まえて、採用した構造種別・架構形式と採用した理由及び構造計画で工夫したこと
RC造、ラーメン架構
構造種別は、振動及び騒音等を抑制できるように、剛性の高い鉄筋コンクリート構造を採用した。架構形式は、◯mの長スパンの無柱空間を構成するため、ラーメン架構を採用した。
長スパンとなる大梁は、たわみやコンクリートのひび割れを抑制するとともに、梁せいが過大とならないようにプレストレストコンクリート造とした。
プレストレストコンクリート梁の取り付く柱の断面寸法は、長スパンによる応力を安全に伝達するために800×1000mmの一般部の柱より大きい断面寸法で計画した。
耐力壁の配置、厚みについて考慮したこと
◯方向は、開口部が多い計画のため靱性型の架構で計画した。
◯方向は、耐力壁付きラーメン架構で計画し、地震力を円滑に伝達するため、◯階〜◯階まで連層耐力壁を計画した。
耐力壁は、内法高さの1/30以上、120mm以上の厚さを確保した。
開口面積は、開口周比0.4を超えないようにした。
妻面に配置した耐力壁に地震力を伝達できるように、十分な水平剛性、耐力を確保できるスラブ厚で計画した。
耐震設計の流れ(学科試験の復習)
一次設計
許容応力度計算及び屋根ふき材等の構造計算
- 荷重・外力による応力計算
- 断面の応力度計算
- 応力度≦許容応力度
- 使用上の支障防止確認
- 屋根ふき材の耐風計算
二次設計
ルート1
規模等による耐震計算ルートの選択
ルート2
規模等による耐震計算ルートの選択
層間変形角≦1/200(1/120)の確認
高さ≦31m
剛性率≥0.6、偏心率≤0.15、塔状比=4の確認
ルート3
31m<高さ
保有水平耐力
Qu≧ Q unの確認
転倒の検討(塔状比>4の場合)
最後に
以上が構造についての要点記述対策になります。近年は、耐震、免震などの地震時の対策や構造設計、避難計画に注目されていると感じますので上記の耐震設計の流れ(ルート)をしっかりと理解しておきましょう。
キーワードを覚えて書けるようになれば、模試や本番でもスラスラ書けるようになりますので、是非何度も繰り返して書けるようになりましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
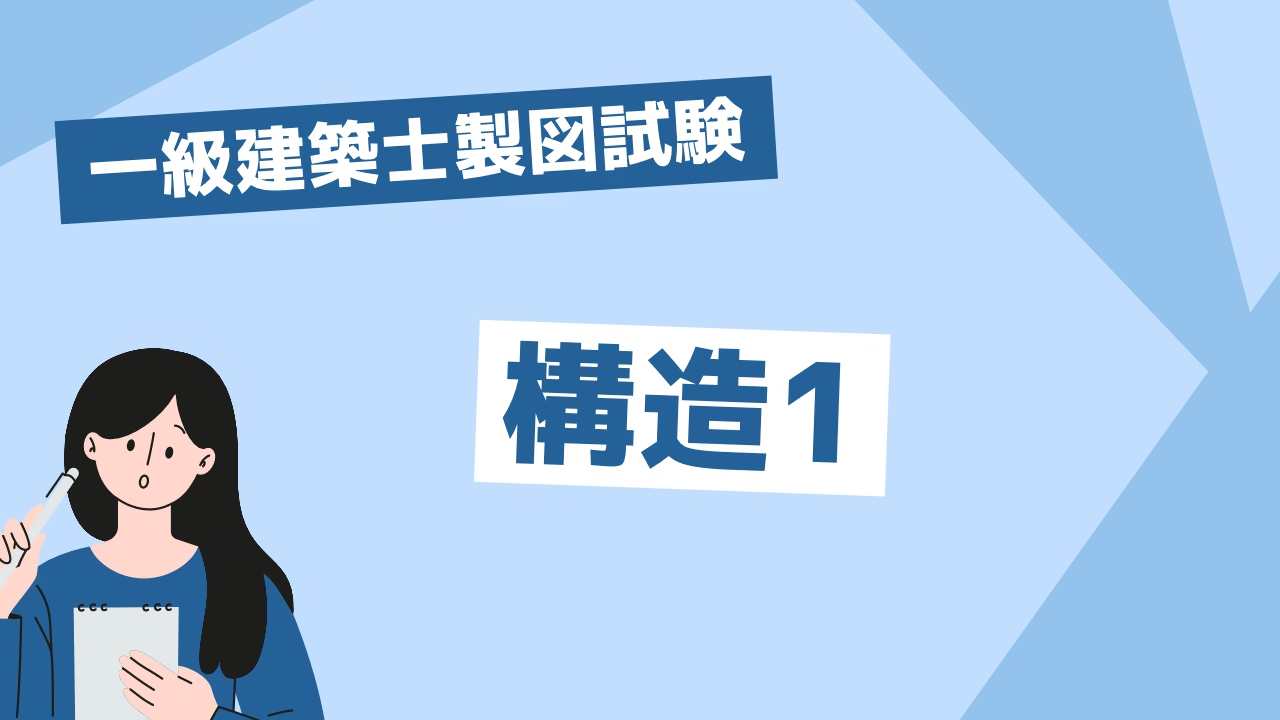


コメント