こんにちは!せこかんくんです。
今回は、既成杭における未固結試験についてまとめました。
未固結試験とは
既成杭工事において本杭を施工する前に試験掘削孔を行い、根固め部から採取することです。
杭先端根固め部の築造が終わり、杭を根固め部に定着する前の段階で、根固め部から採取したまだ固まっていないソイルセメント(未固結試料)を使用します。
未固結試験をすることにより、本杭で築造する根固め部の妥当性を確認することができます。逆に、施工しない場合は、ソイルセメントの品質担保確認するものがないため最近の施工では未固結試験をやることが多くなりました。もちろん未固結試験をやらない場合でも注入前のセメントミルクを採取して試験は行います。
未固結試験の確認は、物性調査と固化供試体に対する強度確認の2段階で行います。
未固結試験は行った方がいい?
結果としては、やったほうが好ましいです。ただし、未固結試験をやるかどうかは杭工法の認定、設計者、監理者、特記事項によります。
未固結試験を行う場合と行わない場合を比較すると、試験をやる場合は本杭の施工前に削孔を行ったり、専用の資機材を使用するのでコストや時間がかかってしまうことは理解しておきましょう。
そのため、工事内訳に入っていなかったり、特記仕様に記載がない場合は無理に実施する必要がありません。
試験を行うのは、埋込み杭工法のなかで杭先端部に根固め部を築造するプレボーリング(拡大)根固め工法および中堀(拡大)根固め工法などがあります。
既成工事をする際は、施工する工法の認定をよく確認しておきましょう。
認定書は、ネットで出てくるような情報は内容が薄かったりするので、施工を行う杭専門工事業者から認定書をもらうようにしてください。
未固結試験を行わず工法認定を取得している場合は、そもそも未固結試験をする必要がありません。(昔からある工法はそもそも未固結試験という考えがなかったので認定に含まれていません。)設計者や監理者などから指定があればやる必要がありますが、認定通りに施工を行えば設計基準を満たす施工になります。
結果が不適合になった場合
未固結試験で十分な結果が得られなかった際は、未固結試料の採取方法、根固め液の配合や注入量、根固め部の掘削・撹拌・混合などの施工方法適用地盤の妥当性などを検討した上で再施工を行います。
再施工にならないためにも専門工事業者によく確認して社内に技術担当がある場合は相談しておきましょう。
試料を採取する際は、材齢3,7,28日の3材齢日の供試体をとるようにしましょう。
全体で3~4Lあれば予備と密度調査用を準備することができます。
最後に
未固結試験をやることで、施工者としても品質向上に努めることができて自信をもって施工することができるため面倒かもしれないですが設計者、監理者と協議をしておいたほうがいい事項だと思います。筆者も監理者からソイルセメントの品質管理をどうやってするのか言及されたことがあり困った経験があります。未固結試験について理解しておくとスムーズに協議・折衝がしやすくなります。ミコケツ??とならないように概要だけでも理解しておくと役立つと思います。
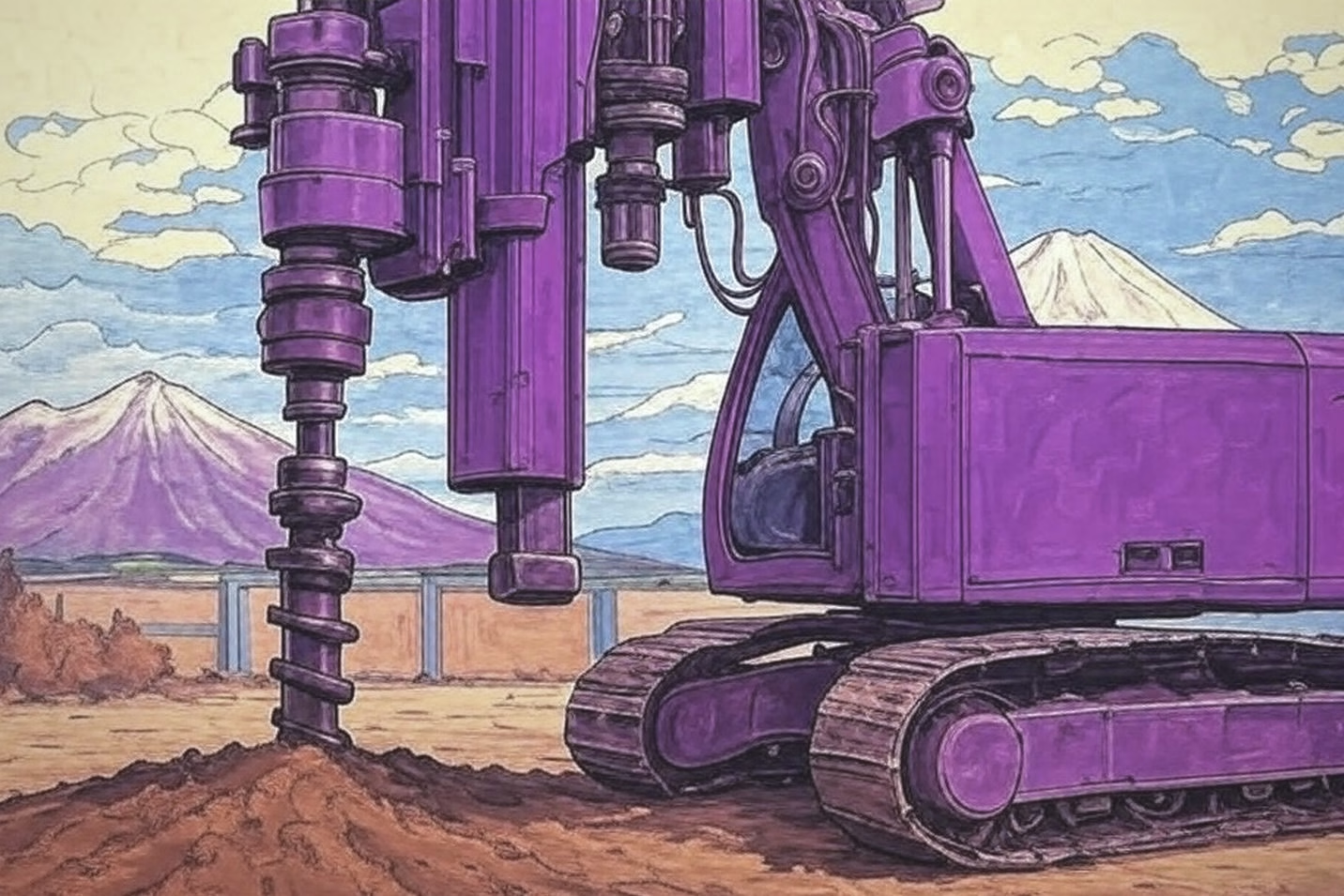
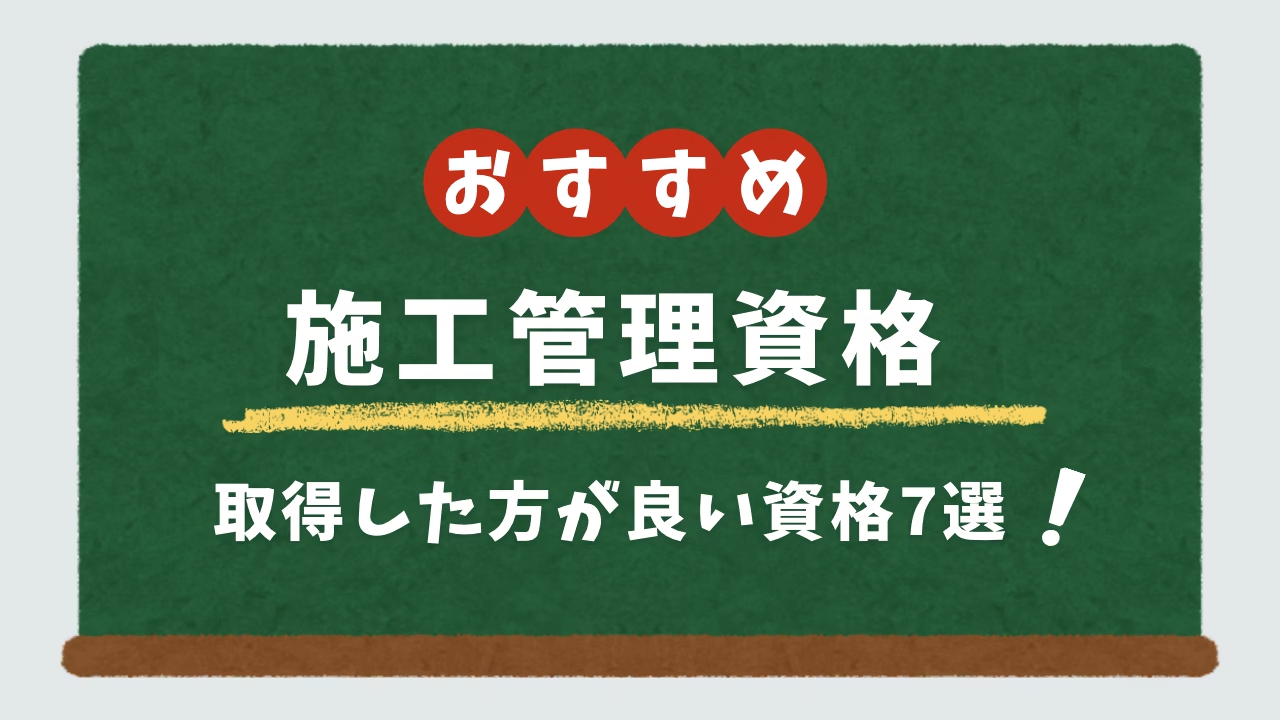

コメント